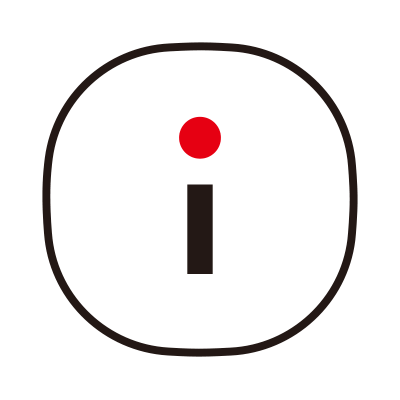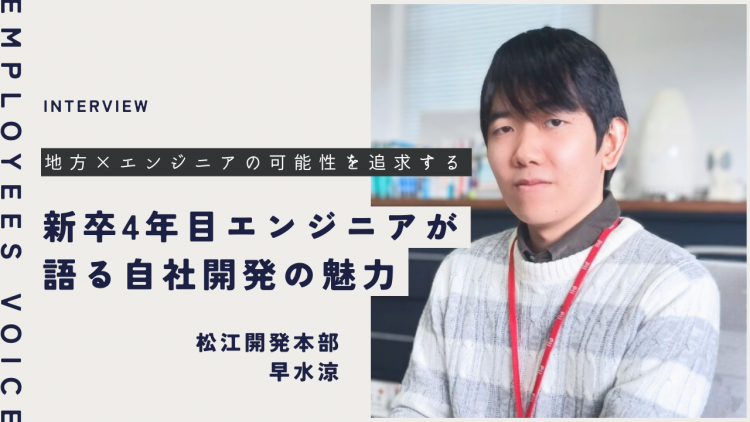21ジャンル82のWebメディア・サービスを運営するイード。そんなイードの主要メディアである自動車専門媒体『レスポンス』から、2024年10月に新たな挑戦として輸入車カスタム専門メディア『[HYPEMOD]』が誕生しました。非常にニッチな領域に思えますが、業界内の空白地帯を埋める形で立ち上がった本メディアには、日本をはじめとした世界各国のアフターパーツメーカー・カスタムショップなどを中心に大きな期待が寄せられています。メディア名に込められた想いから、サイトのダークモード対応という技術的なこだわり、そして輸入車カスタムカルチャーの未来まで、メディア事業本部 オートモティブ事業部 [HYPEMOD]編集長の後藤さんに語っていただきました。
──まずは、後藤さんのキャリアについてお聞かせください。
新卒で入社したのは輸入車の中古車ディーラーでした。最初の1年半は買取営業を担当し、お客様は個人の方が中心でしたが、法人名義の社用車なども扱っていました。全国営業だったので、魅力的な車両があれば遠方まで足を運ぶこともありました。
その後、広報担当としてサイトのコンテンツ管理やSNSの運用も担当するようになりましたが、長期的な視点で業界を見たときに査定業務は自動化される可能性が高いと感じていました。例えば、スキャンするだけで自動車の買取価格が出せるような時代が来るかもしれない―。
転職を意識し始めたころにレスポンスの求人に応募したところ、採用していただくことになりました。自動車業界で働いていたこともあり、レスポンスという媒体は知っていたこと、これまで培った自動車業界での経験と広報担当としてのウェブ制作の経験を活かせる場所だと感じ、入社を決意しました。現在は、タイヤメーカーやアフターパーツメーカーを中心に広告の提案を行っています。

──[HYPEMOD]の立ち上げに至った経緯を、詳しく教えていただけますでしょうか。
輸入車のカスタムを取り扱うメディアが市場から消えてしまったことが大きなきっかけでした。以前は紙媒体を中心に活気があったのですが、様々な理由で姿を消してしまい現在は完全な空白地帯になっています。
この状況は、クライアントにもユーザーにも大きな影響を与えています。例えば、ユーザーの方々は自分の車を『取材してもらって、誌面に載せてもらう』という夢を叶える場所を失ってしまった。また、輸入車業界に進出したい日本のアフターパーツメーカーにとってもPRの機会が大きく減ってしまったんです。
実際、私のクライアントであるアフターパーツメーカーから『輸入車のカスタムカーメディアを作れないか』という相談を受けたこともありました。市場のニーズと業界の現状を見たとき、この領域に特化した新しいメディアを立ち上げる意義は十分にあると確信しました。
──メディアの立ち上げはどのようなプロセスで進められたのでしょうか?
イードが運営する、最新のカーオーディオ情報を配信する専門メディアPush on! Mycar-lifeの編集長から「やってみないか」という提案をいただき、レスポンス編集長とオートモティブ事業部長と話し合いを重ねて実施が決まりました。その後、メディア事業本部長向けにプレゼン資料を作成し、市場の現状や媒体の必要性について説明させていただきました。並行して法務担当者への新規プロジェクト申請や商標の手続きなども進めていきました。企画からサイトオープンまで、だいたい5ヶ月ほどでしたね。
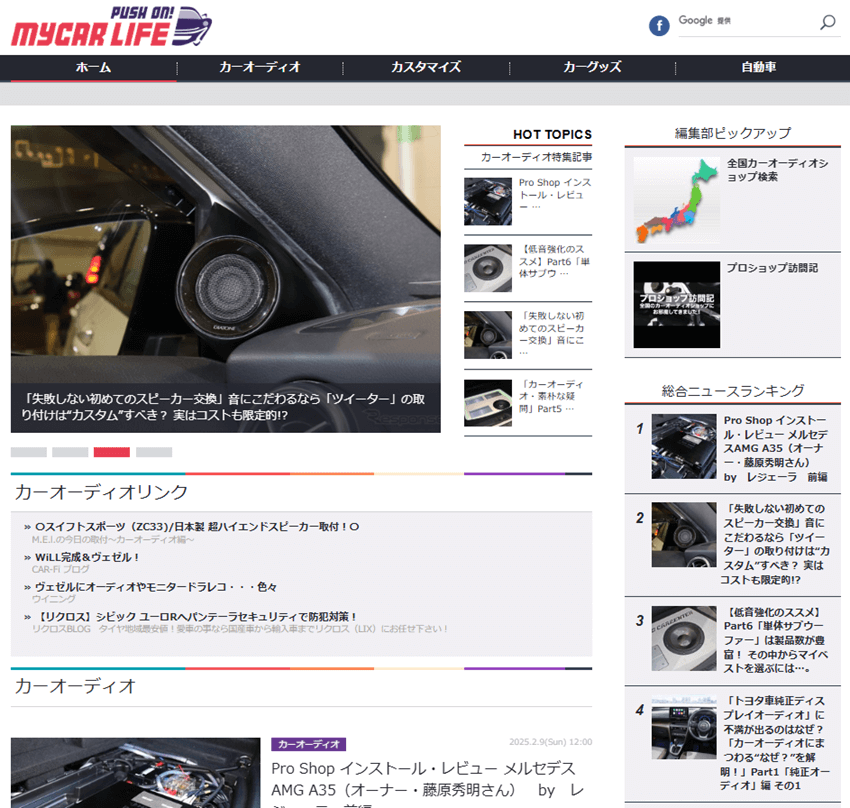
──実際のサイト開発ではどのような過程を経たのでしょうか?
社内のデザイナーやエンジニアの方々と協力して開発を進めました。特にこだわったのが、イードのメディアとして初となるダークモード対応です。デザイナーに相談したところ、既存メディアのレスポンスをダークモード対応させようとすると膨大な工数がかかるという話があったんです。これは、長年運用される中でいろいろな機能が追加され構造が複雑化しているためです。
しかし、[HYPEMOD]は新規開発なので、最初からダークモードを前提とした設計が可能でした。エンジニアの方々と事前に綿密な打ち合わせを行い、複雑な構造を避けながらもダークモード対応を実現。結果として、当社メディアで初めてダークモードに対応したサイトとなりました。

──[HYPEMOD]という興味深い名前ですが、どのような意味が込められているのでしょうか。
まず、メディア名を[]で囲んでいるのは、語呂合わせで”かっこをつける”なんです(笑)。実は大学生時代から好きなバンド[Alexandros](当時[Champagne])から影響を受けています。その頃からずっと記憶に残っていた表現だったので、今回のメディア名にも取り入れました。
そして”HYPE”は英語のスラングで『すごい』『やばい』という意味です。”MOD”は”Modification(改造=カスタムカー)”の略で、直訳すると『やばいカスタムカー』という意味で、端的に言えば『かっこいい改造車を集める場所』というコンセプトを表現しています。スニーカーカルチャーのメディア『HYPEBEAST』からもインスピレーションを得ました。
名前を決める際は、いろいろな候補を考えました。最初は抽象的な名前も検討したのですが、一言で聞いて理解できる、誰が見てもある程度想像できるような名前の方がいいと考え、最終的に[HYPEMOD]に決定しました。サイトのデザインについても、『HYPEBEAST』のような成功事例を参考にしながら自分なりの解釈で落とし込んでいきました。
──他のメディアとの差別化について、どのようにお考えですか。
現状、この領域に特化した媒体がないこと自体が大きな差別化要因になっています。ただし、それ以上に重要なのは掲載する内容の質へのこだわりです。実は、私が取材して『かっこいい』と判断した車両しか掲載していません。これは少し強情かもしれませんが、良質な記事、良質な車、良質なユーザーだけを追求したいという想いがあるんです。
また、単にカスタムカーを紹介するだけでなく、車を取り巻くライフスタイル全体を提案していきたいと考えています。例えば、アメ車が好きな人は単に車が好きなだけでなく、USカルチャー全般に興味を持っていることが多い。音楽や服装なども含めて、本国のライフスタイルへの憧れが根底にあるんです。
車は単なる移動手段や趣味の対象である『点』ではなく、生活全体に関わる存在。そういった視点でコンテンツを作っていきたいと考えています。

──現在の運営体制や、直面している課題について教えてください。
運営面では、外部のライターさんやカメラマンさんと協力しながら記事を作成しています。また、レスポンスとの記事連携も行っています。
課題としては、やはりクライアントの開拓が挙げられます。ただ、手応えは十分に感じており、実際に[HYPEMOD]を見ていただいた方々からは好評で、特にサイトのデザインやコンテンツのおもしろさについて評価いただいています。クライアントの中には『輸入車業界に進出したい』という日本のアフターパーツメーカーも多く、そういった企業とパーツショップ、ユーザーを繋ぐハブになれればと考えています。
──今後の展開について、どのようなビジョンをお持ちでしょうか。
当面の目標はクライアント数の拡大ですが、長期的にはカーイベントの開催も視野に入れています。ただし、大規模イベントではなく、質の高い小規模イベントを目指しています。コンパニオンがいるような商業的なイベントではなく、純粋に車とオーナー、そしてアフターパーツメーカー・ショップが主役のイベントにしたいんです。
また、全国各地には素晴らしいショップやオーナーがいらっしゃいます。SNSの発達で、ある程度の情報は得られるようになりましたが、まだまだ知られていない逸材が眠っています。そういった方々を一つずつ丁寧に取材していきたいと考えています。

──ありがとうございました。
[HYPEMOD] は単なる車両情報の発信にとどまらず、カスタムカーを通じたライフスタイルの提案や、業界全体の活性化を目指しています。また、これまでネガティブなイメージが付きまとうことも多かったカスタムカーカルチャーを、よりクリーンでポジティブなものとして発信していきたいという想いも後藤さんのインタビューを通して伝わってきました。
後藤さんの「良質なものだけを追求したい」という強い信念と、車への純粋な愛が、このメディアの独自性を生み出しているのだと実感できたインタビューでした。